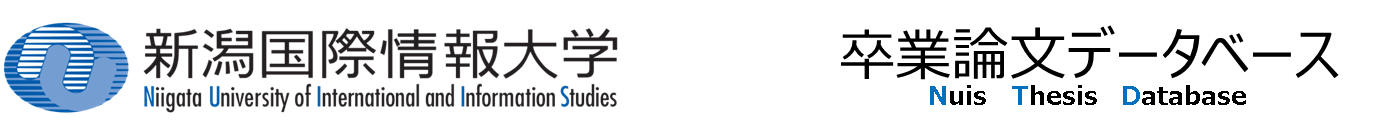抄 録 検 索
[全8100件] : 現在のページ「135」 ---2681個目から2700個目のデータを表示---
 | 一人のユーザの観点からネイティブ広告の認知度、有効性,将来性や今後の動向について整理して、できれば何らかの提案ができないかと考え、卒業論文のテーマとして「ネイティブ広告の有効性」を取り上げた。本論文ではまずインターネット広告について論じ、次に、ネ... | 2016年 | |
 | アルゴリズム作曲法を用いた人間的・機械的旋律の分類Ⅱの抄録です。ここでは論文の概要を簡潔に記述します。 アルゴリズム作曲法は、様々なアルゴリズムによる作曲法である。アルゴリズムで作曲された音列は機械的な旋律になるのではないかと期待してしまうが、機械... | 2016年 | |
 | 外国の本や映画などは、翻訳者によって日本語に翻訳され、出版されている。同じ作品でも多くの翻訳者によって翻訳されており、その表現は翻訳者により異なる部分が多く、解釈が異なる。いろいろな外国語の解釈があるので、翻訳者一人ひとりが異なった解釈をすれば... | 2016年 | |
 | ゲームは古くから、人々の娯楽として存在していた。サッカー・クリケット・トランプ・チェスなど、文武を問わず数多くの種類が存在している。近年では、コンピュータゲームなるものが登場して、瞬く間に飛躍的な進歩を見せた。それは消費者のニーズに合わせて、据... | 2016年 | |
 | 福島原発事故後の小児甲状腺がん多発について、事故との因果関係はまだ認められていない。しかし、私は確実に事故の影響によるものだと考えている。それは、自然に発症する割合が年間100万人に1人である小児甲状腺がんが、福島県では事故後約5年で115人も... | 2016年 | |
 | 本論文はドイツ帝国宰相であるオットー・フォン・ビスマルクが国家の指導者として発揮したリーダーシップを参考にしながら、より良いリーダーになる為にどういった要素が必要なのかを明らかにする事を目的として執筆されたものである。 はじめにの部分では、私... | 2016年 | |
 | 本論は、シンガポールにおける権威主義体制と経済成長の関係を明らかにすることである。マレーシアから独立後、シンガポールは1つの国として生き残っていくために経済発展を最優先として、権威主義体制で国家主導型による経済開発で経済成長してきた。 第1章で... | 2016年 | |
 | 本論文では「戸籍制度」がなぜ現在でも維持され続けているのかを明らかにしていく。中国は現在、農村と都市の格差が社会問題化している。それは特に所得、社会保障、教育の方面に強く出ている。原因は経済成長などいくつかあげられるが、本論文では「戸籍制度」に... | 2016年 | |
 | 本論は社会心理学者エーリッヒ・フロムの『愛するということ』、社会学者アンソニー・ギデンズの『親密性の変容-近代社会におけるセクシャリティ、愛情、エロティシズム-』の2冊を軸として、現代の『愛』の形容とその崩壊、その要因を論ずる。 第一章では、新潟国... | 2016年 | |
 | 2000年代後半から普及されるようになった「スクールカースト」という言葉。これは小学生、中学生、高校生がクラスメイトクラスメイトを値踏みし、ランク付けしていることを指す言葉である。本論文では新潟国際情報大学の学生にスクールカーストに関するアンケート... | 2016年 | |
 | 今の日本は、パソコンやスマホなどの通信機器はなくてはならないものであり、誰しも1度は使ったことがあるだろう。しかし、通信機器を利用するときに多くの人は、無意識に猫背になるような姿勢をとってしまう。筆者自身もパソコンで作業をする際に、気がつくと自... | 2016年 | |
 | 音の出せない環境ではヘッドホンやイヤホンの装着が必要になる。PC作業時や動画の鑑賞などにヘッドホンを長時間装着していると耳が痛くなり、作業に集中できなくなってしまう。そこで本研究では、イヤーパッドを改良しヘッドホン装着時の痛みの低減を検討した。 ... | 2016年 | |
 | 2011年の東日本大震災では、福島原発事故も重なり、いまだ19万弱もの人々が避難したままである 。その長期にわたる避難行動のうちに、多様な問題が生じていた。 本論文の目的は、東日本大震災と阪神淡路大震災の二つの事例を通じて、被災者の避難する権利について考... | 2016年 | |
 | 本論の目的としては、今世界中で問題視されている「難民」という言葉の意味、現状などを明確にしたうえで島国の日本が難民に対してどのような対処をしてきたか、およびその理由を明らかにすることであり、そしてその結果から、今後日本政府が難民認定法についてど... | 2016年 | |
 | 私は以前、テレジン収容所にいた子どもたちが描いた絵を見た。そこには、収容所という過酷な場所で生活しているのにもかかわらず、それぞれの喜びや夢が色濃く描かれていた。子供のほかにも過酷な環境下で生活している人々を、写真を通して見てみたいと思うと同時に... | 2016年 | |
 | <目的> 本論文の目的は、古町商店街の衰退について、なぜ衰退しているのかを現状や外的要因、内的要因を分析し、どのようにしたら古町商店街が活性化できるか考察する。また、他の活性化している地域の事例をもとに古町商店街に適用し、実行できるような活性化の... | 2016年 | |
 | 一章では全体の流れを説明した。二章では問屋不要論におけるネットショッピング、コンビニエンスストアの普及における問屋への影響を調査した。三章では問屋がなぜ必要であるのか、ロジスティクスを主に取り上げ現在での問屋なしでの分業は難しいという観点から問... | 2016年 | |
 | かつて男女の性別役割分担、すなわち「男性は外で働き、女性は家を守る」が明確であった時代であれば女性が働くことについて考える必要がなかった。しかし現代社会は女性が変化し、性別役割分担の意識が弱まりつつある。働く女性も増え、働く女性のための制度や法律... | 2016年 | |
 | 日本古典文学に異文化理解を学ぶ ――異界の概念を手がかりに―― 「異界」それは日本の古典文学に度々あらわれる概念である。人間の未知に対する興味や恐怖を異界という型にはめることで、人々は未知を受容し、表現してきた。本論文ではこの異界の概念に着目し、異界... | 2016年 | |
 | 早朝、起床する際に大抵の人は朝の目覚め感が心地良くない経験とそのまま2度寝をしてしまうことがある。 目覚め感が良くない原因としては睡眠時の状態が関係している。ヒトの睡眠にはノンレム睡眠とレム睡眠という状態があり、ノンレム睡眠時には睡眠段階が深く、... | 2016年 |