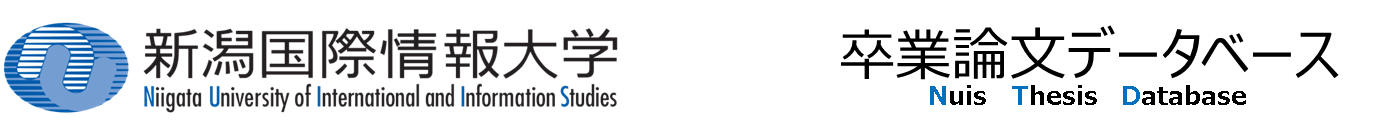抄 録 検 索
[全8100件] : 現在のページ「220」 ---4381個目から4400個目のデータを表示---
 | 本論文の目的は、日本文化の対外発信力としてのホラー映画、つまりジャパニーズホラーの原点にあるものを、他国の作品との比較、さらに何故ジャパニーズホラーは海外で受け入れられているかという視点から考察していくことである。これら基本の問いを論じるため、第... | 2010年 | |
 | この論文の目的は、上海協力機構の実体を明らかにすることである。上海協力機構の前身、上海ファイブはソ連崩壊後の国境安定化のために発足したものであった。しかし、多分野での協力を行うことを目的に2001年に発足した上海協力機構は参加国を増やして拡大してい... | 2010年 | |
 | 携帯電話が便利になり誰もが所有するようになったが、メリットだけがあるわけではない。この利用により、携帯電話の「パーソナル化」が進み、友人間でのコミュニケーションのとり方、家族間のコミュニケーションのとり方に変化がでてきた。携帯電話利用が人間関係... | 2010年 | |
 | 「空を、この土地のぬくもりを、どうやって売り買いしようと言うのだ。そんな考え方はわれわれには理解できない。すがすがしい大気や湧きたつ水を所有しているのは、われわれではない。それなのにどうやって、われわれからそれを買おうと言うのだ。この大地のどこを... | 2010年 | |
 | 女性は、男性優位の中で様々な差別を受けてきた。女性たちは、日々男女差別に苦しみ、国連の「女性の地位委員会」を始めとして、女性の権利を訴えてきた。そして、こうした女性たちの幾度とない困難を乗り越えてきたひとつの成果として、国連においては1979年に女... | 2010年 | |
 | 従来、韓国の葬制は朝鮮時代からの儒教を基にした死生観によって行われてきた。しかし、その葬制は1960代以降から大きく変容された。 第一章では、葬儀の変容についてみてきた。その背景は、病院内の葬儀場の普及、強制的な法令、現代の国民生活による意識変... | 2010年 | |
 | 本論文では、マス・ツーリズムに代わる新たな観光形態の一つとして注目されているヘリテージ・ツーリズムについて、アンコール遺跡群を例に挙げて研究することにより、ヘリテージ・ツーリズムの成果、課題、可能性を論じることを目的としている。ヘリテージ・ツーリズムを評価する上での3つの重要なポイントから考察した結果、ヘリテージ・ツーリズムを形成するにあたって、地域住民や外部の人々の一人一人がヘリテージとしての価値を認識することが最も重要であるということを論じた。 | 2010年 | |
 | In today’s world of globalization、 the number of foreigners coming to Japan continues to increase every year. Large numbers of foreigners are not only Tokyo but also in Niigata. In this world、 more people need to see foreign countries and people... | 2010年 | |
 | 衰退している佐渡について考える内容となっている。 主に、観光と世界遺産という観点から結論を導いている。世界遺産登録運動が盛んに行われている佐渡で、実際に各地の先行例を挙げてどのようになっていくのかを考える内容となっている。世界遺産登録を推進する方へのヒアリングを行うこともでき、最終的な自分なりの結論を導くことができた。 | 2010年 | |
 | コーヒー豆生産者は全世界で2500万人を有し、コーヒー産業に関わる人口は全世界で5億人とも言われる一大産業である。しかし、この一大産業であるコーヒーには、生産者の貧困が問題となっている。コーヒー豆生産国の多くは発展途上国である。生産国の多くは外貨獲得... | 2010年 | |
 | 世界最大の鯨であるシロナガスクジラが捕鯨業でその頭数を減少させ、絶滅の危機に瀕しているとされたことから他の鯨類もシロナガスクジラと同様に絶滅の危機に瀕しているという認識が1970年代から広まり、捕鯨問題へ発展した。それにより、欧米諸国のような反捕鯨国... | 2010年 | |
 | 序論 日本ではこれまでも女性差別が問題視され、男女平等に関する政策が進められてきた。例えば1999年6月には男女の人権が尊重され、男女が性別による差別を受けることなく、能力と個性を発揮できる社会の実現を目指す「男女共同参画社会基本法」が施行され、これに... | 2010年 | |
 | 日本女性における子育てについて参考文献をもとにみてきた。戦前の日本は約8割が農業従事者で、女性は子供を育てるよりも、嫁としての労働力が期待されていた。そのため、子育ては現役を退いたお年寄りや、年長児と呼ばれる子供が、乳幼児の世話をしていた。つまり... | 2010年 | |
 | 私が卒業論文のテーマに選んだのは、老老介護だ。現在の日本は、高齢人口が増加している。そんななかで、老老介護が急速に増えてきている。本稿では、老老介護が増加した原因を解説しながら、私たちがどうすれば良いのかを説明していく。 第1章では、老老介護が... | 2010年 | |
 | 「不妊」というと、女性の悩みのように考えられ、事実これまで、男性社会の歴史的背景から、すべて子どもができないのは「女性のせい」とされてきた。しかし、今や不妊の原因の半分は男性にあるといわれる。その原因とは何なのか。 人間の精子は、健康な男性でも、... | 2010年 | |
 | 80年代、ニューヨークやロンドンをはじめとした、国際金融センターの繁栄を現す言葉として現れた「世界都市」という概念は、多くの都市を魅了し、都市のあるべき姿の目標とされ、世界の都市がその姿を追った。日本の都市、東京もそのひとつである。1国の都市であ... | 2010年 | |
 | それゆえ本論文では、幼児教育が始まってから現在までの教育制度の在り方の変化を明らかにし、その上で現在行われようとしている幼保一元化に迫っていく。幼保一元化とはどのようなものなのか。またその具体化の一例として生み出されてきた認定こども園とはいかなる... | 2010年 | |
 | かつて、結婚は大抵の人が一定の年齢に差しかかればするものであった。その形態は仲人結婚や政略結婚など、職場や親戚、地域コミュニティからの紹介が確立されていた。今までは結婚相手と出会い、ゴールインするというのは自然の流れであったが、現在では地域コミュ... | 2010年 | |
 | 私がヒッピーに関心を持つきっかけになったのは、洋服の影響からだった。様々なファッションスタイルの中でも愛と平和、自然回帰、サイケデリック(薬物による幻覚症状から来るイメージ)などをテーマとした服装は明らかに他のスタイルとは違い、タイダイ(絞り染め... | 2010年 | |
 | アジア宇宙機関設立の可能性(ESAとAPRSAFからの分析) 宇宙開発は科学だけでなく、軍事とも密接に関係している。それは宇宙ロケットが弾道ミサイルの技術を基礎としており、観測衛星や有人飛行においても過去には米ソの人工衛星を用いた相互の偵察(現在も偵察... | 2010年 |