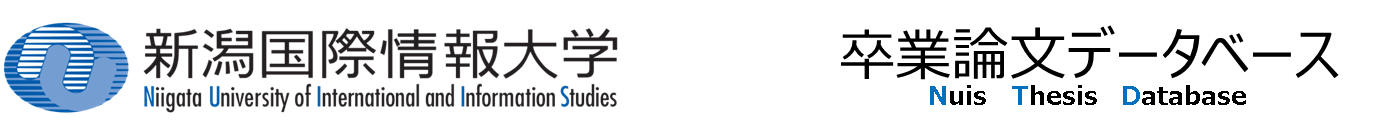抄 録 検 索
[全8100件] : 現在のページ「255」 ---5081個目から5100個目のデータを表示---
 | 近年、食品業界における賞味期限や原材料の偽装や捏造といった企業による不祥事が連日のように報道されている。2007年1月には、テレビ番組での情報の不正な操作によって納豆の売上げが一時的に伸びたといったことを耳にした。 偽装や捏造といった行為は、企業の... | 2008年 | |
 | 観光情報などの案内システムの利用者は、案内対象の位置や形状などに関する正確な案内情報を求めている。すなわち、利用者へ可能な限り正確な情報を伝えることは案内システムにおいて重要なことである。 三次元グラフィックスを用いた案内システムの実現において... | 2008年 | |
 | 日本は中国に対し、1979年から政府開発援助(ODA)を実施してきた。その額は国際協力銀行の資源ローンと合わせて6兆円を突破している。だが、その結果中国は日本の厚意に感謝し、日中友好の実りを上げたのかと言えばそうではない。 中国の一般国民は日本からのODAの... | 2008年 | |
 | 私は、週末限定で派遣会社アルバイトとして、携帯電話販売促進キャンペーン業務の現場責任者であるディレクターとして携わっているのだが、その業務の1つに報告書作成業務がある。この報告書作成業務は通常帰宅後PC等で作成するのだが、これを休憩時間や移動時間など... | 2008年 | |
 | インターネットが一般家庭にまで普及した現在、インターネット上に存在する様々なコンテンツやサービスが、パソコンさえあれば家庭でも簡単に受ける事ができるようになっている。オンラインショップ、オンラインアミューズメント、ソーシャルネットワークソサエティ... | 2008年 | |
 | 今日、様々な企業で情報システムが導入されている。 システムを導入するということに成功すれば顧客サービスの向上、作業の効率化に繋がり、仕事の簡略化や顧客からの信頼を得られる他多くの利益を生み出すことができるが、失敗しまった場合は今までの苦労が全て... | 2008年 | |
 | 化粧品業界では販売チャネルの拡大が進んでいる。それに伴い、消費者の化粧品の購入先は、ドラッグストア、コンビニエンスストアなど、多様になってきている。その中でも、近年、通信販売から購入する消費者が増加している。2005年度における通販化粧品の市場規模... | 2008年 | |
 | 計算作業能率は覚醒水準が影響するといわれており、また、この水準は朗読による発声や、音楽聴取による聴覚刺激により、上昇させることができるとされている。したがって、自ら声を発し、相手の声を聴くという会話も、計算作業能率を上昇させる可能性が考えられる... | 2008年 | |
 | 本研究ではPLCの転送速度と漏洩電波について検討した。転送速度に関する研究では、PLCモデムとイーサネットケーブルを用いてLANを構築し、FTPによる転送速度を計測した。その結果、PLCで構築したLANはイーサネットケーブルによる一般的なLANよりも転送速度の面で劣る... | 2008年 | |
 | ホームページは、今や企業のだけでなく、個人で作成できるくらい簡単に開くことができる。しかし、マークアップ言語のHTMLのみ使ったものだとホームページは質素なものになってしまう。そこで、ホームページ上に動く絵やゲームなどの仕掛けを作ることで見る側をそそ... | 2008年 | |
 | この研究における目的は、新潟市民がなぜバイパス道路を利用するのか実態を明らかにし、その中から新潟市近郊バイパスの利用価値を決定して、バイパス道路を利用することが、しない場合と比べて目的地への時間短縮になるのかを検証することと、渋滞損失時間を算出す... | 2008年 | |
 | 近年、若年層の読書ばなれが問題視されている。先行研究は、高校生の読書量が中学生よりも少ないという調査結果を示している。だが、なぜ年齢と共に読書ばなれが進行していくのかは研究されていない。 そこで、本研究では高校生という時期に着目し、高校生の読書... | 2008年 | |
 | 本研究は音楽経験が有る人も無い人も、曲の作成・アレンジで楽しめる「MIDIファイルを作成するプログラム」を目的として行った。 第1章では、研究を行った動機、研究の目的についての説明を行った。 第2章では、研究に使用したJava言語について、成り立ち、特徴、... | 2008年 | |
 | 私は、最も身近な母が銀行に勤めているということもあって、以前から金融情報システムムに興味を持っていた。金融は、日本国内だけでなく世界を動かすためになくてはならない世界の中心的なシステムであり、銀行と銀行の間はどのように繋がっているのかということを... | 2008年 | |
 | 今後、日本では高齢化が今以上に進むことは確実である。21世紀半ばには、国民のおよそ2.5人に1人が65歳以上という超高齢社会になることが予測されている。その時代を支えていかなければならないのが、私たちの世代である。 しかし、従来、高齢化問題は高齢者側だ... | 2008年 | |
 | 本研究では、縦方向に流れる文字の可読性について調べることを目的とした。文字数、文字の並び方、スピード、日常生活の違いによってデータを分類し、比較検討した。 本学生10名を被験者とし、8つの条件を設定し、被験者1人ずつ実験を行った。被験者に読ませる文... | 2008年 | |
 | MBAは、米国において企業経営を科学的アプローチによって捉え、経営の近代化を進めるとの考え方のもとに、19世紀末に登場した。簡単にいうと、MBAとは、世界レベルで通用する経営学の知識とネイティブな英語ができることを示す資格と考えられている。1970年代後半に... | 2008年 | |
 | 本来インターネットは多くの学術機関や企業の研究機関に接続されるようになっており、当時インターネットを行う上でのサービスが電子メール・電子掲示板・ファイル転送(FTP)・遠隔ログイン(Telnet)などがあった。これらのサービスを受けるためにはコンピュータの専門... | 2008年 | |
 | まえがき ミスや失敗は、人間ならば誰にでも起こるものである。しかし、そのミスにも様々な種類があり、ミスを犯す背景にはそれなりの要因が存在する。 同じ文字を速い速度で繰り返し書き続ける「急速反復書字」により、意図した文字とは全く別の文字を書いてしま... | 2008年 | |
 | 近年、スポーツクラブの合併や売却、スタジアム観客動員数の低下、テレビ視聴率の低下など、スポーツクラブ関係者はもちろん、ファンにとっても残念なニュースを耳にすることが多くなってきた。スポーツクラブが何年も同じ方式で運営されているため、ファンが飽きて... | 2008年 |