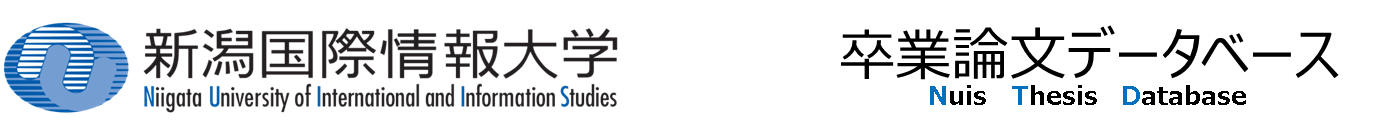抄 録 検 索
[全8100件] : 現在のページ「289」 ---5761個目から5780個目のデータを表示---
 | 子どもの虐待は新しい社会現象ではない。子どもの虐待が最近急増しているのではなく、取り組みが進んだために子どもの虐待の報告件数が最近急増しているというのが正確である。日本では子ども虐待の発生件数を把握するための統計、調査が少ないので、既存の数値か... | 2005年 | |
 | 大学2年生の時に4ヵ月間、中国の北京市に留学した。ようやく留学生活に慣れた頃、北京の夜空に星が見えないことに気づいた。星があまり見えないという視覚の感受は、ただちに、環境破壊の結果としての理解につながるわけではないが、北京市内を見ても、道路の路... | 2005年 | |
 | 1957年、人類は初めて人類自らの手で造った人工衛星「スプートニク1号」を宇宙へと打ち上げた。以来、米ソ両国間では宇宙開発競争が繰り広げられてきた。そして、1969年のアポロ計画では、ついに人類は月へと到達することができ、「人類は宇宙から地球を... | 2005年 | |
 | グローバル化が進む国際社会の中で、人々の移動は、モノやカネ・サービスの移動と同じように活発に行われている。しかし、その人々の移動には、自らが望んで国境を越えるものや、生きるために自らの意思に反していても仕方なく国境を越えるものがある。国境を越え... | 2005年 | |
 | 現在に日本は、少子高齢化の到来により多くの問題を抱えている。そこで、われわれの生活に大きな影響を及ぼす、国民年金問題を取り上げ卒業論文とした。本論分では、年金不信の根本を追求し、公的年金の抱える問題を明らかにした上で、様々な年金改革案の検証を行い... | 2005年 | |
 | 私がこのテーマで研究しようと思った理由は、小さいころからテレビが大好きだという事と、テレビ局でアルバイトをしたことによって、テレビを見る側、作る側の立場からテレビ・リテラシーについて、また制作現場の裏側を明かしていきたいと思ったからだ。 ニュース... | 2005年 | |
 | 本書は大きく分けて5つの部分から構成されている。 1つ目は第1節「本書の成り立ちと目的」である。ここでは著者Uschi Billmeierとママディ・ケイタの出会いから本書を作成する経緯が書かれており、本書の性格を理解するうえで一番重要な部分である。 2つ目は第2... | 2005年 | |
 | 全体主義という言葉を聞くとドイツやロシアを想起し、恐ろしい政治体制であったということがわかる。そしてそれは過去の政治体制であったとも思ってしまう。しかし全体主義はいつどこでも出現する可能性を含んでおり、もう出現することのない政治体制とは言うこと... | 2005年 | |
 | 韓国はIT先進国と言われている。韓国インターネット情報センターの統計によると2004年6月現在、韓国のインターネット人口は3、067万人で全人口の約68.2%の人がインターネットを利用している。韓国国民は現在、接続の段階を越えて日常生活の道具としてインターネッ... | 2005年 | |
 | 京劇は、中国文化を代表し、世界中でよく知られている。しかし、京劇のイメージは派手な化粧や衣装、雑技などがあるが、その詳細についてはあまり知られていない。京劇はどのような技術で成り立っているのか、また、どのような時代を経て、現在に至っているのかを... | 2005年 | |
 | 1980年以後、中国は「改革・開放政策」の推進によって急速に発展してきた。その結果、国民の生活水準は大きく向上し、中国の国力も大きく増大した。2001年には念願だったWTOに加盟し、世界経済の一員として自由貿易体制下での発展を目指し始めた。「世界の工場」とも... | 2005年 | |
 | 日本は明治維新により近代国家建設に着手して以来、第一次世界大戦までに日清戦争、日露戦争という2つの大きな戦争を経験した。とりわけ1904年に起こった日露戦争はその後の日本の対外政策の方向性をも決めてしまった。さらには新興国家でアジアの東端に位置する小国... | 2005年 | |
 | 外交官杉原千畝(1900~1986)は、第2次世界大戦中、欧州リトアニアの日本領事代理として、ナチスドイツの迫害から救出するため、ユダヤ人に6000枚のビザを発行したとして世界に賞賛されることとなった。その人道的行為がゆえに、千畝の偉業は現在、日... | 2005年 | |
 | 現在の日本とアジア―中国、韓国、朝鮮との関係において、さまざまな問題を抱えている。過去において日本が行ったアジア植民地化問題に大きな関係があるように思え、日本が行った植民地化政策と戦争の多くが当時の思想家によってどのように捉えられ、正当化されていっ... | 2005年 | |
 | 私が中学生の頃、英語の授業で『ポカホンタス』というディズニー映画を見た。『ポカホンタス』は、1995年6月23日に初公開された映画で、それは、米国先住民女性と白人男性の恋の物話である。WEB上のディズニーサイトにある『ポカホンタス』の説明によると、「舞台... | 2005年 | |
 | 人種問題を取り上げた映画を観て、アメリカ社会における差別とは何かを考えるようになった。差別は単に肌の色が違うことだけを差別とするのではなく、社会に対する様々な物の見方や価値観の相違によっても差別は生じてくるのではなかろうか。そのためには、南北戦... | 2005年 | |
 | 現在、在日社会は大きな転換期にある。それは在日社会が一世、二世から三世・四世へと世代交代が進み、国籍・民族・価値観などが多様化してきているということである。また、現在日本国内には、在日外国人だけで約100万人、外国人観光客、外国人留学生などを含める... | 2005年 | |
 | サハリン島(樺太)は、北海道の北にある宗谷海峡を挟んだ北緯約45度から55度に存在する島である。日露戦争の結果、樺太は北緯50度以南を日本帝国(以下、日本)の領土とし、北緯50度以北をソヴィエト社会主義共和国連邦(以下、ソ連)の領土とした。 サハリン残留韓... | 2005年 | |
 | 卒業論文には、漠然と私自身が感心がある「伝統工芸」に関わることについて、調べてみたいと考えていた。私にとって、伝統工芸品は身近なものであり、親しみが持てるものだが、いま伝統工芸は、衰退へと向かっていると言われている。では、どうして衰退へと向かっ... | 2005年 | |
 | 植民地朝鮮から日本への「強制連行」についての研究は、1962年に朴慶植氏が初めてその用語を使用し、その後着実に研究が進んできた。今やその用語は政治的にも学術的にも完全に定着し、教科書にも「強制連行」と記述されていることが多い。しかし、その研究に... | 2005年 |