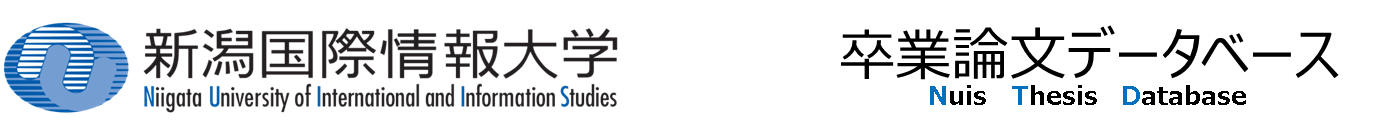抄 録 検 索
[全8100件] : 現在のページ「348」 ---6941個目から6960個目のデータを表示---
 | 私は中国における大陸と台湾の統一問題にたいする研究をするにあたって過去の歴史を探る必要性があるように感じた。そうした歴史を紐解くにあたり過去、現在、未来という問題にはじめてせまることができるように思う。 20世紀前半の中国においては戦争と革命の半世紀... | 2001年 | |
 | この論文では、ユダヤ人を「保守派」と「改革派」の2つのグループに分けて、彼らの歴史について紹介した。そもそもユダヤ人は、ユダヤ教で定められている独特の戒律を守って生活している。この2つのグループの特徴として、「保守派」はこの戒律を伝統的に守ってお... | 2001年 | |
 | 身近である「ごみ」から環境問題を考える。「循環型社会」とは、大量消費社会に代わって持続可能な社会を達成するための新たな社会のイメージをいう。廃棄物対策の優先順位を、発生回避、再生利用、適正処理の順とし、生産、流通、消費、廃棄という社会経済活動の前... | 2001年 | |
 | 親が子どもに暴力を振るう。もしくは、精神的に暴力を振るう。このことは、親であれば許される行為であるのだろうか。たとえそれが、子どもの死に至るような行為であったとしても許されるのであろうか。そして、それは「しつけ」と言えるのであろうか。現在、児童虐... | 2001年 | |
 | 太宰治の文学に、彼の生まれ故郷である津軽の風土がどのように関わっているか、というのが本論におけるテーマである。ある作家の作品や作風といったものを、風土というフィルターを使って見るということは一つの危険性を孕んでいる。それはその作家の全てを風土の特... | 2001年 | |
 | 世界に様々な伝統や風習がある中で、私は中国の類い希なる「纏足」を取り上げた。この纏足というのは、女性の足を大人になっても成長させずに約10センチという大きさに止めておく風習である。親指を除いた4本の指を足の裏へ折り曲げてつま先を尖らせるのである... | 2001年 | |
 | 1 歴史的見解 2 地理的見解 3 国際法的見解 | 2001年 | |
 | ハリウッド映画におけるアジア人の扱われ方について、<イエローフェイス>という本を素材にして歴史的に検証しました。 | 2001年 | |
 | 最近のニュースには未成年の犯罪が目立ち、学校は荒れていると叫ばれるようになった。いじめ、不登校、学校の抱える問題は数多くあるが、その中で私は学級崩壊をとりあげた。というのも、学級崩壊に対する教師や教育評論家、文部省などの意見はよく見かけるが、実際崩壊を引き起こしている生徒の意見を取り上げたものが少ないと思ったからである。この研究は生徒の意見を十分に考慮し、学級崩壊の要因や、改善策を模索したものである。 | 2001年 | |
 | 日本人だけでなく、世界の多くの人々誰もが一度は目にしたことがある白いビーグル犬。それが「スヌーピー」である。この犬と人間のちびっ子たちが繰り広げる、普通だが愉快で味のある日常を描いた漫画が「ピーナッツ」である。この作品は、アメリカで1950年にチャー... | 2001年 | |
 | ケネディは、大統領としての第1期の3年目に暗殺されたということ、彼の内外の政治に反対する勢力が強かったこともあり、独立革命の達成や、南北戦争を戦い抜いて連邦を維持したというような功績を挙げたわけではない。では、今日のケネディに対する評価の高さはど... | 2001年 | |
 | 中国は56の民族が共存している多民族国家である。しかし、その民族の内訳は皆同じ割合ではない。1民族である漢民族が9割以上を占めているのである。そして、残りの55の民族で1割弱を占めている。この55の民族を少数民族という。このように人数において、圧倒的... | 2001年 | |
 | 今年で戦後55年目を迎えた。この55年という年月を長いと感じるか短いと感じるかは人それぞれだろうが、戦争を体験していない世代、特に戦後の貧しい時代も知らない高度経済成長期以後に生まれた若い世代の人々にとっては、「戦争」は遠い過去の出来事である。確かに... | 2001年 | |
 | 巨匠に必要なのは「安らぎ」であるとキリスト(と思われる人物)は語る。人は闇を恐れるが、闇の中で視界が開けないからこそ希望やら一般に好ましいとされるものが潜んでいる可能性が見える。光ばかり見つめて闇の、安らぎのない世界から二人は救われた。光ばかりが善良なのではない。 | 2001年 | |
 | この論文の題名は「日ロ経済関係と日ロ関係の現況」とする。それは現在の日ロ間に存在する問題や、ロシアの現況を詳しく書いたものである。ロシアの中でも後進地域は極東地域だといわれている。極東地域に特に注目して、ロシアの現況をまとめた。極東地域の現状は、... | 2001年 | |
 | 私は、今日においては避けては通れない原子力問題の意味・意義は何かをテ-マとして選びそこに潜む問題点や矛盾性を、ウラン残土の不法投棄があった鳥取県の人形峠を例にして示し、これからの原子力、真の原子力の正しい姿について研究してみた。我々、新潟県人に... | 2001年 | |
 | 日本のODAは外交手段と成りうるか 佐藤 武雄 高橋ゼミ 11097046日本のODAというものは民間のボランティア活動とは異なり、税金や郵便貯金等の公的資金を原資としており、援助にあたって供与国の「国益」が絡んでくる。しかも現時点において援助は「世... | 2001年 | |
 | 現在電車は、便利な乗り物である車に押されて運行回数減少といった不便さをもたらしている。車と同じ路上を走るバスはなおさらだ。ここ最近、まともに路線バスの世話にはなっていないような気がする。当然のことながら、本数減少や子会社移管など、サービス低下の... | 2001年 | |
 | シンガポールに友人ができてからシンガポールの文化に興味を持つようになった。調べていくうちにその多様性にすっかり魅せられてしまった。シンガポールには、7割を超える華人の他に、マレー系、インド系など多様な人種がそれぞれの伝統を守りながら共存している。... | 2001年 | |
 | 私がなぜテクノミュージックをテーマに書こうと思ったのかというと、聞いてみなければ絶対に分からない音楽の素晴らしさを文字だけでどれだけ伝えられるのか、それを試みてみたかったからだ。私の好きな音楽が「テクノミュージック」というあまり多くの人に聞かれていない音楽だったこともあり、テクノミュージックとはどんな音楽か、私はなぜテクノが好きなのか、なぜテクノを聞くようになったのか、テクノの魅力とは何なのかということをもし言葉だけで伝えられたら嬉しいと思ったのだ。 | 2001年 |