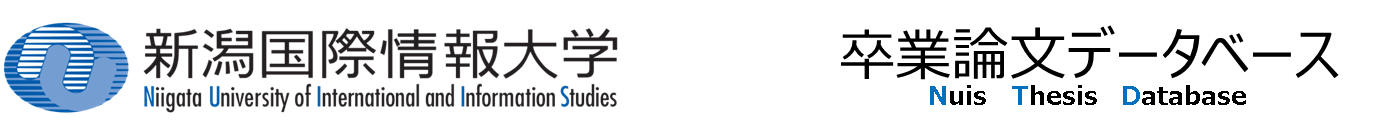全 項 目 検 索
[全8100件] : 現在のページ「219」 ---4361個目から4380個目のデータを表示---
 | |||
| 世の中には、戦争、テロ、貧困などたくさんの暴力が存在する。まだ記憶に新しい「9・11」テロ事件や、カンボジアでの地雷問題、各国各地で起こっている内戦、貧困、感染病などがその例であり、国連、ユニセフ、NGOなどたくさんの団体がその暴力を救おうと活動... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 本稿では、弥彦山のブナ林の構造について調査を行った。調査は2009年10 月から12月にかけて、東側斜面5箇所と西側斜面7箇所に方形区を設置し、胸 高直径1.3m以上をもつ木本の樹種名,胸高直径,生育位置を記録した。 次に調査結果をもとに胸高断面積比、個体数比に... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| この論文は、現在、世界各国で取り組まれている京都議定書に関し、その成り立ちや交渉の過程を追ったものである。現代では、環境問題の悪化が大きな問題として取り上げられている。ヨーロッパで起こった産業革命以降、人類はそれまでの薪や木炭といったエネルギー... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 本論文のねらいは、水資源問題の現状と課題、特にジェンダー不平等に焦点を当てることによって、問題の重要性を明確にし、克服へ向けた国際パートナーシップの可能性を考察していくことにある。 今世界では、集中豪雨などによって引き起こされる洪水の被害や砂漠化... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 本論文の目的は「フード・マイレージ」という指標がどのように生まれ、どういった役割を果たすのかを明らかにし、環境問題との関係性に触れながら私たちの生活とどのように結びついていくのかを考えることである。 本論文の構成は以下の通りである。 第1章では、フ... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 戦前の家族法(明治民法)で、「家」制度という言葉が用いられた。法律上の「家」制度とは、すべての国民を家に結びつけ、戸主を通じ国民を統括しようとした制度である。 「しかし、昭和20年の太平洋戦争で敗北し、日本が受諾したポツダム宣言の民主主義的傾向ノ復... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| この研究に取り組むきっかけは、筆者は、大学二年生の時、留学したことである。中国は発展している中で、環境問題やマナーの問題など数多くの、問題を抱えている。2008年8月8日に北京オリンピックが開催されたことについて、環境問題、マナーの問題、インフラ整備な... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 新潟ではここ数年の間に数回の地震が起こった。それらの地震の震源地は長岡~柏崎地域を含む上・中越地域である。それらの震源は比較的にせまい地域に位置する。また、その地域には柏崎刈羽原子力発電所が立地している。活断層が多く存在し、今後も地震が起こると想定されることから、これらの地域の地盤変動、とりわけ活断層の状況を把握することは重要である。そこで、本稿では調査地域の従来の研究をまとめた。次に実際に現地にて活断層と地形との関係を把握することを目的とした。 | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 本論文の目的は、現代社会で問題となっている新興宗教に関する問題、いわゆるカルト問題を取り上げ、特に脱会カウンセリングに焦点を当て、その現状と可能性について、とくに法的なことがらにも視野を広げつつ、考察していくことである。 本論文の研究を通じて、... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 本論文では破壊的カルトが信者に教義を教え込むために実際に行っていた方法がどのようなものだったのかなどを取り上げた。 第1章では破壊的カルトが宗教と何が違うのかということについて特徴をあげた。一体破壊的カルトとはどういった団体をさすのかなど、破壊的カ... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 世界の人口は大量に増え続けており、近い将来、資源・エネルギー・環境など多くの地球的・人類史的な問題を深刻化させる恐れが大きい。中国は現在大きな社会変動の時期にあり,それがアジア・世界へと大きな影響を及ぼしている。急速な経済成長によって生じた経済... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 本論文では外国人ムスリム(イスラーム教徒)と日本人女性との国際結婚をテーマに取り上げる。本論文の目的は、日本人ムスリマ(女性イスラーム教徒)に焦点を当て、国際結婚がもたらす異文化接触がどのように当事者や周囲に影響を与えていくのかを明らかにしようと... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 本論文では現在まで急速に広がり続けているフェアトレードの現状、そしてこれからの未来の来るべき世界へ向けた展望や課題を考察していく。 私たちにとって「普通」と感じることは、自分達の狭い範囲での感覚であり、世界で考えたら「特別」なことだったりするの... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 本論文の目的は、塩の社会的な重要性を改めて考察することである。現在の日本では、塩が果たしてきた社会的な役割があまり意識されず、単なる調味料として認識されているからである。塩は、人類の歴史の中で大きな影響を誇ってきた。塩が活用されてきた多岐にわた... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 今年テレビで「水」を特集したニュース番組を観た。聞けば現在、世界人口が増加し続けているという問題が懸念されている中、それと同時に生じる問題が「水問題」だと言う事を知った。これから水が足りなくなるかも知れないのである。それを「水危機」と呼ばれてい... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は2007年の第4次評価報告書において気候システムの温暖化には疑う余地がないことを科学的に示し、その原因のほとんどが人為起源によるものである可能性が高いことを示した。しかし、現在でも地球の気候システムは完全には判明し... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 2009年8月3日に日本で初となる裁判員裁判が開かれた。これは2009年5月21日に施行された「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、無作為に選ばれた国民が裁判に参加するという制度である。 この制度は今までの職業裁判官と一緒に一般市民が裁判に参加... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 日本では、小学校に通うことが義務付けられている。その結果、こどもは文字や計算、社会についてなどを学ぶ。そして、将来、社会に出たときには一通り困ることなく生活できるようになっている。それは日本だけではなく、世界中どこの国も同じだと思っていた。 し... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 「食べる」という行為は生きていくうえで欠かせない行動であり、もちろん長期にわたって欠かせば命にかかわる。この豊かになった食生活を見直すため「食育」が今見直されている。しかし、だからと言って何を食べても許されるのだろうか。食育基本法の前文には「自... | |||
| 2010年 | |||
 | |||
| 日本には日本国憲法という国の最高法規が存在する。1946年5月3日に施行されてから現在に至るまでの64年間1度も改正されてこなかった。憲法改正の案は出てはいるが、憲法を改正するべきであるという改憲派と、現憲法は現在のまま守っていくべきであり、改憲は憲法を... | |||
| 2010年 | |||