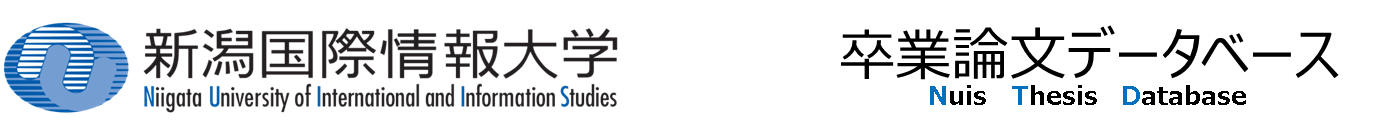全 項 目 検 索
[全8100件] : 現在のページ「278」 ---5541個目から5560個目のデータを表示---
 | |||
| 地方債は地方自治体にとって、事業の際の資金調達面で重要な役割を果たしている。しかし、2000年4月1日に施行された地方分権一括法と三位一体改革により、国から地方自治体に対して、税財源の移譲、および権限の移譲が進んでおり、その一環として地方債制度の改革... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 「裏日本」という言葉は今の10代・20代には聞きなれない言葉である。その意味すら知らない人がほとんどであろう。私自身、大学の講義で「裏日本」という言葉が取り上げられるまでは、耳にしたこともなかった。「裏日本」とは後進的な意味合いを含む語である。... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 歴史は進んでいる。現在も、そしてこれからも進んでいく。私は今、そんな歴史の中に身を置いて生きている。 「歴史」という言葉は、学校の教育課程においては過去を学ぶことだが、本論文で論じていきたい「歴史」は、決して過去に限ったものではなく、時間の流れそ... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 「ジェンダー」,「男女平等」といった言葉が、ほぼ当たり前のように聞こえてくる社会になってきた。ジェンダーという言葉が「ジェンダー主流化」の取り組みと共に国際社会に浸透し始めたのは1995年の北京世界女性会議がきっかけであると思われるが、それを受けて... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 筆者が中国のマスメディアに興味を持ったのは、2003年の10月下旬に中国で起きた西安寸劇事件の報道がきっかけである。当時のマスメディアの報道によると、西安市の西北大学で日本人留学生の卑猥な寸劇に中国人学生が怒って抗議活動が広がったこの事件は、中国メデ... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 筆者は大学生活で、チベット族の衣装を着たり、留学でチベット族の女の子と知り合ったりしたことでチベット族の文化に興味を持つようになり、研究のテーマとすることにした。本研究はチベット族の服飾を取り上げ、そのあり方や移り変わりを中心に研究したものであ... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 長洲一二の著書『自治体の国際交流』で「民際外交」という考え方に出会った。国が主体ではなく市民主体の外交。この考え方は非常に新鮮であった。外交という言葉のイメージから、外交とは国同士が行うことだと考えていた。しかし、『大辞泉』小学館 によれば、外交... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 韓国には国際リゾート地として有名な済州島という島がある。最近は日本での韓国ブームによって韓国へ訪れる日本人観光客の増加傾向にある。済州島は「オールイン」や「チャングムの誓い」といった韓国ドラマの舞台になったところとして知られ、その撮影場所を訪れる... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 韓国は美容整形先進国と言われるほど整形がさかんに行われていて、それは老若男女を問わなくなっている。韓国では、美容整形を受ける人の割合は増え、整形も前向きに捉えている。若い女性でも手術費用を負担できるようになったことが、美容整形の増加につながって... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 初等教育における社会科には、理想の「国民像」という点でどのようなメッセージが込められているのだろうか。本論文では、初等社会科教育にあらわれる理想の国民像を、日本とイギリスの社会科教育に焦点を当てることで、比較・検討していく。これによって「社会科... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| サムスングループは干し魚や青果類を扱うサムスン商会から始まり、急成長を遂げ、韓国を襲った経済危機を乗り越えた。サムスン電子における、DRAM、SRAM、携帯電話、超薄膜トランジスター液晶表示装置など複数の分野で世界のマーケットシェア1~3位を占める... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 2004年7月に行われたサッカー・アジアカップでの中国側の日本に対してのブーイング騒動や、2005年4月、中国各地で「反日」デモが繰り広げられたことでも知られるように、近年でも日中間の摩擦は絶えず起きている。中国における「反日」感情は、依然とし... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| EUの共通軍事行動の構想は、これまでどのように展開されてきたのだろうか。 これまで私は、ヨーロッパは軍事面ではアメリカに遠く及ばない国であるという認識を持っていた。それは確かに誤りではないが、EUは失敗を教訓として今日までの発展を遂げてきた。コソボ・ボ... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 第二次世界大戦が終了した後、米ソ対立が激しくなり、ヨーロッパとアジアで一つの国になるべきはずであったドイツと朝鮮半島はそれぞれ分断国家としての道を歩み始めた。ソ連、冷戦構造が崩壊し始め、ヨーロッパの冷戦構造の最前線に位置していた東西ドイツは統一... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 本研究ではスポーツといじめから、ジェンダー概念のひとつである「男らしさ」について考察する。主な対象となるのはスポーツやいじめの問題が起こりやすいと思われる小中高の教育過程の少年である。 第1章では、時代とともに変化してきた「男らしさ」について言及... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 本研究のテーマは、現代社会における生命政治を分析することである。このテーマを選択しようと思ったきっかけは、ジョージ・オーウェルの『1984年』やレイ・ブラッドベリの『華氏451度』を読んだことである。なぜなら、それらの作品の中の管理社会では、主体性が剥... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 本論文では、サッカーをつうじて、ナショナリズムについて考察する。2004年の夏のアジアカップでの、中国人による反日運動、ワールドカップアジア最終予選での日本人の熱狂的な応援などを取り上げながら、現在のサッカーにおける日本人のナショナリズムのあり... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 世界には様々な言語が存在している。近年国際交流が進む中で第二外国語を学ぶ人が増えつづけている。国際情報大学でも英語、中国語、韓国語、ロシア語を学ぶことができる。特に中国語は、日本語と同じ漢字を使う言葉として比較的身近に感じる言語である。しかし、... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 時期区分を、1期は1945年~1948年、2期は1948~1955年、3期は1955年~1968年とする。以下の三点に焦点を絞り、在日朝鮮人の教育がどのように変化していったかを明らかにする。?民族団体がどのように変化して、それが在日教育にどのような影響を与えたか。?民族教育... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 人々に愛されたチェーホフ アントン・パーロヴィチ・チェーホフ(以下チェーホフ)は1860年に、タガンローグで6人兄弟の3男として生まれました。 一章では、彼がなぜ愛されたのかと、彼の経緯について述べてあります。 チェーホフ家には、元々たくさんのお客が訪れ... | |||
| 2006年 | |||