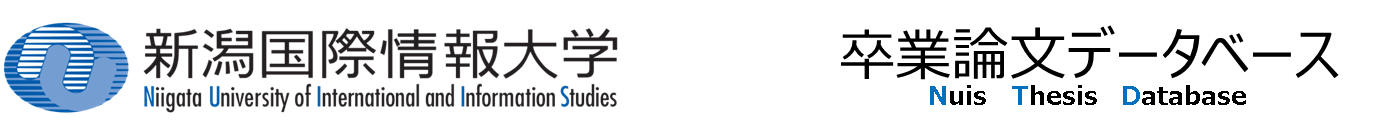全 項 目 検 索
[全8100件] : 現在のページ「276」 ---5501個目から5520個目のデータを表示---
 | |||
| 日本には約60万人の在日韓国・朝鮮人が住み、日本に帰化した人たちを含めるとさらにたくさんいる。そのなかには日本で活躍している人も多いが、自分が在日韓国・朝鮮人だということはあまり公にはしない。それは日本社会全体による圧力なのではないか。 日本へ帰... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 2005年4月に行われた日中外相会談において、中国の李肇星外相は「中国には中日関係をよくする願望と誠意がある。しかし日中間では歴史認識、靖国問題、最近の教科書問題は深く中国ならびにアジア人民の感情を傷つけた」と発言した。しかし、本当に日本の行動だけに... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 私がこのテーマでの論文を書いた理由として、1冊の本がきっかけであった。その本とは斎藤美奈子の『戦下のレシピ 太平洋戦争下の食を知る』岩波新書(2002年)である。この本では初めて飢餓の実態を直接感じ取る事ができた。戦後60年という年月が経ち今は飽食時代、現... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 私が今回バレエに興味を持ち、卒業論文にするきっかけとなったのは『ジゼル』というばれである。このバレエは『ジゼル』とは現在でもほぼ初演に近いかたちで受け継がれている最も古いバレエである。このバレエをテレビではじめてみたとき、ダンサーの時に力強く、... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 今日の日本は少子化が進み、その結果高齢化社会に突入している。さらに2005年12月22日に厚生労働省が発表した人口動態統計の年間推計によれば、日本の人口が2005年に初めて減少に転じることが分かり「人口減少社会」を迎えた。 日本の総人口は1億2768万7000人であ... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 本論文の目的は、コメの輸入自由化による米価低落に対して新潟県内の稲作農家はどのような対応をしていくべきなのか、そして将来的に稲作を存続させていくことが出来るのかを明らかにすることである。 私の住んでいる新潟県は全国的に見ても稲作が盛んでコメ作りを... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 本研究のテーマは、「標準語」、「方言」の社会的地位を考察しながら、現代社会における、「母語」が排除される社会構造を研究し、社会的に「劣っている」と判断される「方言」を擁護するのが目的である。 そもそもコミュニケーションのための道具としての言語に... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 私たちの生活している市町村の多くは、第2次世界大戦後のいわゆる『昭和の大合併』時に誕生したものである。その後も、合併は小規模には続けられてきたが、全国的な大規模なものではなかった。 戦後の日本は高度経済成長を遂げ、世界有数の経済大国になった。また交... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 本論で、「自治体制度」を選択したのは、大学2年次からゼミで研究していたこともあり、国際交流や災害対策など、自治体の活動に新しい可能性を期待しているからである。自治体外交において、環日本海圏で枢要な位置にある日本が、特に「友好」という視点から、ロシ... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 筆者は中国の新聞である人民日報のひとつの記事に興味を持った。その記事の見出しは「孔子の智慧を吸収、現代問題を解決」である。中国で行なわれた孔子生誕2555周年の国際学術研究討論会の記事である。見出しからも分るように、「儒学思想の祖である孔子の教えを... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 今の私たちと同世代の人たちは「慰安婦」問題という言葉を知らない人が多いと考えられる。「慰安婦」問題を教科書から無くしてしまおうといった動きすらある。こういった社会では、この問題を解決することは困難だと考える。そういった「慰安婦」問題を知らない人... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 2004年10月香田証生さんがイラクのバグダットで首を切られた遺体で発見された。イラクで拉致され殺されたのだ。この後、香田さんは亡くなったにも関わらず「自己責任論」という言葉がテレビ、新聞などで騒がれ、小泉首相は「残念だ。残虐非道な行為に改めて憤りを覚... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 人権というものは人が生まれながらにして持っている権利であるが、それを世界的に保障している国際連合の人権条約というものとその活動内容について本論文で見ていきたい。 世界人権宣言をはじめとして、現在の国連は自由権規約(1966年)、社会権規約(1966年)... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 私がこのテーマを選んだ理由は、2005年中国で起こった反日デモ・これからの中日関係が、今現在とこれから先の将来、私の中で一番関心があることだからである。 私は本学の留学制度で中国に留学をした。留学に行く前は、少しは中国に対して良いイメージはあった。... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| グローバリゼーションが現在のHIV/エイズ問題を色濃く映し出しているといえる。HIV感染者/エイズ患者の実に95パーセントが途上国に集中しているが、彼ら/彼女らの中でエイズ治療薬を手にできる患者は限られている。エイズは、1981年にアメリカで最初の患者が確... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 1994年4月、南アフリカで初の全人種参加の総選挙が実施された。それはアパルトヘイト(人種隔離政策)撤廃の集大成であり、民主主義政治の始まりであった。ネルソン・マンデラ率いるアフリカ系黒人政党、ANC(アフリカ民族会議)が政権政党となったことにより、黒人... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 韓国ではいまだに男女差別が根強く残っている。それは、世界的な指数である男女平等指数という指数から見ても、そのようなことが言える。その男女平等指数では日本が38位、韓国が54位で、超大国と言われるアメリカは17位になっている。そしてその上位をほとんどが... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 2006年で日本と中国が国交を回復して34年になり、両国共に不可欠なパートナーとなっている。しかし、現在の日中関係は決して友好な関係であるとは言えない。 2004年に実施された世論調査で「親しみを感じない」人が日本では過去最低の63.4%、中国... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 1960年代頃からタイは経済成長を迎え、都市は仕事の機会が豊富で魅力的な場所として位置付けられていった。そこで、都市に労働を求めて農村地域等から多くの人々が移動してきが、都市で暮らすためには物価が高いために都市の立地条件が悪い路地裏や高速道路脇... | |||
| 2006年 | |||
 | |||
| 第1章では、行動経済学がどのような学問なのかを述べる。一般的な経済理論を批判する形で、人間の行動は予測不能であるということを証明していく。そして過去の研究事例を紹介し、筆者の考える理想の夫婦の理想の労働分担の形態を述べる。 第2章では、まずアン... | |||
| 2006年 | |||