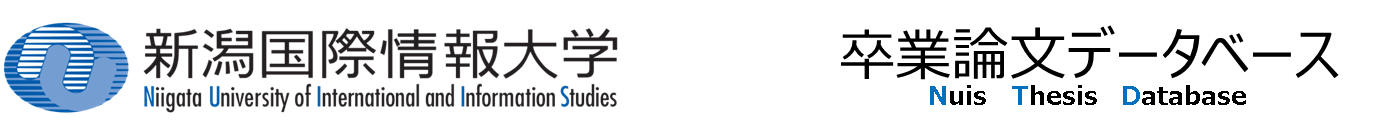抄 録 検 索
[全8100件] : 現在のページ「175」 ---3481個目から3500個目のデータを表示---
 | 本論は、摂食障害者の約90%が女性であるということに目を向けたものである。大きくわけて拒食症と過食症に分けられる摂食障害は、カーペンターズとして活躍したカレン・カーペンターの死によって一般に認識されるようになった。しかし、拒食症はただ食べずに痩せて... | 2013年 | |
 | 本論文では、ペリー来航から遡り、幕府や密航留学生たちの外国意識の変化について言及していきたいと考えている。 アメリカは中国への中継地としてどうしても日本が必要となり、使節団を送り、どうにかして日本を開国させ、リードしていこうと考え、1853年、アメ... | 2013年 | |
 | 2000年以降、日本の数あるコンテンツの中でも、アニメ・漫画などが「COOL」と評価され、世界での人気が高まってきている。そこで戦略的に国を挙げて海外展開を行えば、人気を付加価値にし、収益源にできるポテンシャルは十分にあるはずである。しかし日本の海外に向... | 2013年 | |
 | 近年多くの大学でキャリア教育の必要性が認識されている。これは大学が果たす役割として、従来からの大学教育に加えて学校から社会への移行を橋渡しする機能が重要性を増しつつあるからである。この背景には、雇用環境の変化によるフリーター志向の広まりやニートと... | 2013年 | |
 | 近年、家庭において育児に積極的に携わる父親や、介護に携わる夫、息子が見られるようになってきた。その一方で、労働市場における看護や介護、保育などの生きるために人の手を必要とする人たちの生活を支えていく労働、すなわちケア労働は長らく女性職で在り続けて... | 2013年 | |
 | 本論文は、韓国企業サムスンがなぜ世界的に企業成長をなしたのか、その成長要因を追ったものである。 まず、先行研究で、サムスンの1993年の新経営宣言を契機に改革を行っていった内容(技術、人材、ブランド面など)を集約した。そして、その中で、日本企業とサ... | 2013年 | |
 | 「一夜子」、「富良日」、「詠」、こういった名前を初めて見て、なおかつ正確に読める人は多くはないであろう。ちなみにそれぞれ「ひよこ」、「ぷらす」、「ながむ」と読み、実在する子どもの名前である。こうした名前は近年、「DQNネーム」、「キラキラネーム」と... | 2013年 | |
 | この論文ではミーム学を用いて、ツイッターにおける成功しているミームと失敗しているミームを検証していく。この論文のキーワードは大きく分けてミームとツイッターである。 まず一つ目に、ミーム(meme)とは、リチャード・ドーキンスの「利己的な遺伝子」ではじ... | 2013年 | |
 | 学校生活が原因で死を選ぶ子どもがいる現状がある。 日本でも韓国でも、学校がある。子ども達はそこで勉強をしたり、人間関係を学んでいく。上級の学校に通うためには試験を突破しなければならない場合もある。しかし、学校という箱の中で、あるいは試験に合格... | 2013年 | |
 | ハワイは買い物や遊び、大自然を一気に満喫でき、そして手軽に外国気分を味わうことのできる場所である。今日の日本社会でも、ハワイといえば「ビーチ」「ショッピング」「自然」「癒し」など、観光客の欲望が叶えられる「楽園」というイメージが強い。このように... | 2013年 | |
 | 2011年11月15日、日本とブータンの国交樹立25周年を記念して、ブータン国王夫妻が来日した。それを契機に、国民総幸福量(GNH)という独自の考え方を国家の指標として打ち出して、世界中から注目を集めるブータン王国に関心が集まり、日本でもブータン王国ブームが訪... | 2013年 | |
 | アネクドートとはロシアの口承文学である。ロシアの政治や文化、日常生活などをテーマにジョークや小話といった形で作られ、昔からロシアの人々に親しまれてきた。その起源はピョートル大帝の時代にさかのぼり、彼の時代に西欧化が進められ、ヨーロッパの文化が取り... | 2013年 | |
 | 長い間、幸福度測定の尺度として用いられた国内総生産(Gross Domestic Product)に代わる尺度として、近年では多くの学者が経済面以外の要素に注目し始めた。たとえば、GDPに変わる新しい尺度として国民総幸福度(GNH)である。具体的には、精神面、家族関係、社... | 2013年 | |
 | 本論文では、大塚マスジドを取り上げ、日本に住むムスリムの生活と文化を明らかにした上で、2011年3月11日に発生した、東日本大震災の被災者支援活動の取り組みについて考察する。 小山田ゼミでは、2012年3月14、15、16日に東京ゼミ合宿を行い、見学先は、東京... | 2013年 | |
 | 少子高齢化が世界の国々で進んできている。その中で、少子高齢化について大学の講義で学び、少子高齢化が与える影響を少し知ったが、もっと深く少子高齢化の実態を理解し、問題点を把握する事で将来の私の生活でどのように考えていけばいいか、また国としてやるべき... | 2013年 | |
 | 第2次大戦後、ガット体制の下で工業製品の自由化は進められたが、農産物は例外だった。ところが80年代、工業製品で大きな貿易赤字を累積したアメリカは、国際的に比較優位な農業製品の自由化を求めてきたのであった。コメの100%国産を前提する日本は強力に反対論を... | 2013年 | |
 | 大学全入時代と言われる現在、大学は大衆化し、大学進学率は50%を上回っている。それに伴い、大学のレジャー化や大学生の学力低下などのさまざまな問題点が指摘されている。多くの学生は偏差値や大学のブランドによって進学希望先を決定し、志望校に入学できなかっ... | 2013年 | |
 | アルジェリアは1830年から1962年までの132年間、フランスの植民地に置かれた。そこで「原住民」と呼ばれたムスリムたちは、市民権を与えられず差別的な待遇を受けていた。フランスの行ってきた入植・同化政策が失敗に終わり、アルジェリアをフランス化」することがで... | 2013年 | |
 | 18世紀、ロシアはピョートル大帝の政策により、西欧化、近代化が推し進められた。建築物や生活様式、学校制度や日常にかかわるもののほとんどが、ロシアの伝統的なものから、新しいヨーロッパ風に変わった。衣服もそのひとつである。西欧化の影響を受け、宮廷服も... | 2013年 | |
 | 本論文では北海道の代表的な観光地である富良野市について、観光地への発展過程と現状の分析を通じて、今後の課題や可能性について考察することを目的とする。 富良野市は第1次産業である農業が基幹産業であったが、近年ではサービス業を中心とした第3次産業... | 2013年 |