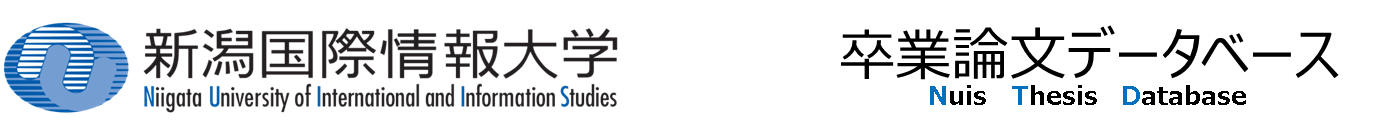抄 録 検 索
[全8100件] : 現在のページ「74」 ---1461個目から1480個目のデータを表示---
 | 私は、高校時代からアルバイトとしてマクドナルド新潟駅南店で勤務しており、大学生になると同時に時間帯責任者(スイングマネージャー)として店舗の運営を任されるようになった。社員の代理責任者としての立場で店舗を運営しながら勤務することで、アルバイトとい... | 2021年 | |
 | 私は、2019年5月14日から小型無人航空機(ドローン)の操縦の練習をしている。ドローンに興味を持ったきっかけは花火をドローンで空から撮影している映像を見た際に、普段見ることができない景色を目にし感動したことがきっかけである。練習をしているうちに、ただ... | 2021年 | |
 | 本論文では、新潟県新潟市西区赤塚に位置する御手洗潟という湿地について私が抱いた疑問を文献調査、インタビュー調査、イベントへの参加を通して得られた情報から明らかにしていくものである。御手洗潟を選んだ理由としては、赤塚に関する文献を読んだことがきっか... | 2021年 | |
 | The main topic of thesis is: Linguistic landscape in aquariums. My main research question is:How is language used inside aquariums in Niigata Prefecture? The first sub question is: How is language used in public signs in aquariums? The second sub ... | 2021年 | |
 | This thesis has analyzed spoken discourse of a movie called Summer Wars released in 2009. Three types of conversation and talk were selected from the first and middle parts of the movie conducted between Kenji who is a high school student and thre... | 2021年 | |
 | マス・メディアは、エドゥサ革命や共産圏などでの革命により、反政府運動の土台を作り、多くの政権を崩壊させ、人々が一つとなる役割を担った。ソーシャルメディアは、国民自らが発信者となり、意見や情報を発信するという役割を担った。携帯電話さえあれば、いつでも、どこでも情報を共有 でき、ネットワークはつながっていくのである。その一方で、ソーシャルメディアは、ドゥテルテ政権で見られたような例外状態を作り上げ、多くの人権侵害を引き起こしており、ソーシャルメディアは民主化を促進しているとはいえないのである。 | 2021年 | |
 | 学校の怪談は、1980年代後半から民俗学者・常光徹によって発見された口承伝承の1つである。1990年代、常光が発表した定型化した学校の怪談は全国に広まり、学校の怪談ブームと呼ばれ、小・中学生を中心に絶大な人気があった。本論文では、ブームと先行研究をふまえ... | 2021年 | |
 | 本論文は同性婚について日本と海外諸国を比較して論じたものである。比較した国はアメリカと台湾の2国だ。また、同じ観点から比較をし、歴史、現在の制度、今までの判例と判決の3点から考察をした。比較、考察をした上で、今後の日本の同性婚についての向き合い方や筆者の意見を述べている。 | 2021年 | |
 | 日本では戦後から温泉ブームが続き、近年では外国人観光客も日本の温泉に入りに来るようになった。日本人は公衆浴場において当たり前のように裸で入浴しているが、外国人には奇異にうつるという[中野 2016b:110-111]。外国人の利用が増加してから、温泉施設は外... | 2021年 | |
 | 本論文では、ウィーダ『フランダースの犬』を題材に、貧困層の子どもにとって、ルーベンスの絵画は何の象徴であったのかを明らかにしていく。また、ウィーダが感じていた社会問題への不満について注目し、その後の作品にどのような影響があったのかを考察していく。... | 2021年 | |
 | 観光は、日常生活圏を離れ、心身の気晴らしや保養、日常生活からの脱却を目的として非日常を追求する諸活動という認識のもと、常に人の動くところに存在する事象であり、観光の要素を取り入れた新たな学問が派生している。本稿の主題である観光地理学においても、... | 2021年 | |
 | 今日、少子高齢化をはじめとした社会問題の解決を図るため、内閣府を主体に地方創生と呼ばれる施策が行われてきた。この施策は各対象によって内容が異なり、経済や人口問題など、内容は多岐にわたる。国としては法律や制度などの施策に取り組む一方、県、市では他県... | 2021年 | |
 | This thesis has analyzed spoken discourse of a movie called Titanic released in 1997. Four types of conversation were selected from the first and middle part of the movie conducted among Jack Dawson, Rose DeWitt Bukater, Ruth Dewitt Bukater, and C... | 2021年 | |
 | This thesis has analyzed spoken discourse of a movie called Breakfast at Tiffany’s released in 1961. Three types of conversation were selected from the beginning, middle, and the last part of the movie conducted between two people living in a same... | 2021年 | |
 | This thesis has analyzed spoken discourse of a movie called Stand by Me released in 1986. Two types of conversation were selected from the middle and last part of the movie conducted among four children in America. The talk has been investigated... | 2021年 | |
 | 本論文では、主に日本の諜報機関の歴史や現在の自衛隊の情報機関等を調べ、これからの日本の諜報機関のあり方について私自身の考えを主張するものである。目的としてはグレーゾーンの事態における日本の現状、情報機関の重要性の認識と共有、就職先への理解を深める... | 2021年 | |
 | まず、はじめにで何故このテーマを選んだのかと研究の最終的な目標について簡潔に説明した。その後、序章で、里親制度の簡単な解説と仮説を提示した。その仮説とは、やはり子供は、施設よりもより家庭的な環境で育つことが、大切であるというもので、その仮説に基づ... | 2021年 | |
 | 今日の日本は超高齢化社会に突入し、多死社会だといわれている。日本では「死」がタブー視される風潮があり、教育機関でも死の教育(デス・エデュケーション)がなされることはなく、死について考える機会が少ない。死は誰にでも訪れることであり、目を背けてはいけな... | 2021年 | |
 | 本論文では、ヒトラー誕生から権力掌握に至るまでの期間にしぼって、イアン・カーショーの研究をもとに、ヒトラーの人間像を把握し、他の研究者の視点とも比較しつつ、ヒトラー著『わが闘争』の真偽性を検討する。 ヒトラーの家庭環境には特筆すべきことはなく、大... | 2021年 | |
 | 本論文では、シャルリ・エブド襲撃事件について取り上げ、襲撃事件の全体像はもちろん、風刺画の特徴、殺害された編集者の功績についても検討した。また、フランスの表現の自由を獲得した歴史的背景、表現の自由の成り立ちに着目した。 事件の要因は、シャルリ・... | 2021年 |