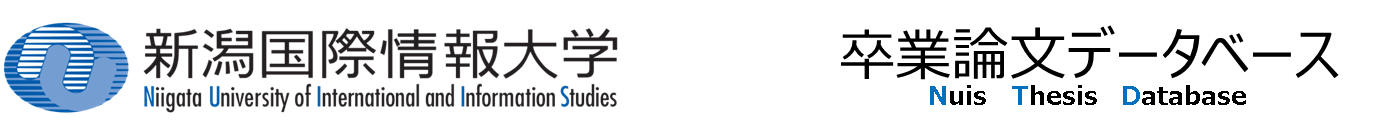全 項 目 検 索
[全8100件] : 現在のページ「341」 ---6801個目から6820個目のデータを表示---
 | |||
| 日本と韓国は1965年の国交正常化交渉以来、貿易・投資・人的交流は飛躍的に増大したが、1990年代を通じアジア経済危機にかけて日韓両国間の貿易・投資は停滞し、両国関係はやや疎遠になった。しかし、2002年日韓協同開催のワールドカップや、韓国で日本映画の公開な... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| インターネット技術は、今や一部の専門家だけのものではなく、世間一般の人が関り合いを持たざるを得ないものとなった。インターネットをどれだけ知り、どれだけ有効に活用できるかどうかが、経済競争における勝ち負けの鍵を握ると言われるようまでの成長を遂げた... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| 人は生活をする限り移動しなければならない。それは障害者、足腰の弱い高齢者も同じことである。しかし、日本の街中にあるバリアは彼らの移動を邪魔している。駅の階段、バスの乗降口の段差、歩道の狭さ。このようなバリアを取り除き、誰もが住みやすい街や建物を目... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| 近年、情報ネットワーク化が大きく進展し、セキュリティーチェックのためのIDやパスワードを入力する機会が増えてきた。このようなシステムではパスワードは本人しか知らない情報であるということを根拠にしてユーザ認証を行っているが、パスワードを盗み見られて... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| ファジィ理論は人間の大局的・概括的な知的情報処理、つまり人間が得意とする”あいまいさ”の近似的なモデルを扱う理論のことである。 本研究で扱うファジィ制御はファジィ推論を用いて行われる。ファジィ制御は熟練者が行っている対象を的確に捉えた意思決定を比較... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| 三次元コンピュータグラフィックス(3DCG)とは、コンピュータで制作された立体形状の画像や映像の事を指す。Adobe PhotoshopやIllustratorで描かれる平面的な画像とは異なり、ゲームや映画の分野でよく見られる奥行き感のある画像で、現在CGの主流となっているも... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| 本研究の目的は、インターネット利用の47都道府県差を明らかにする事である。近年の新潟県における普及率は平均を下回っている。1997年の時点では5%差であったが、2000年の時点では20%にまで開いている。インターネットが生活に密着している現状で、地域格差は重大な... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| 卒業研究に何を行うか考えたとき、最初に思いついたことはWebカタログの作成であった。次に、何のカタログを作るかということを考えるに至ったとき、やるなら好きなもので、興味深く、意欲的に取り組むことができるものを題材にしたかった。そこで車を取り上げるこ... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| 日本のマスメディアの中でも特にテレビやインターネットの媒体が大きな変容を遂げ、社会に大きな影響を与えている。この論文では特に若年層に対して悪い影響を与えるマスメディアは、主にテレビとインターネットの媒体である事と、その対策について検討した。自分... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| 現在、個人情報流出による被害は表面化した程度に過ぎない。見ず知らずの電話やダイレクトメールが自分宛に送られてきたり、名簿の売買が行われたりなど、今後ますます増え続け、被害が大きくなり現行の法律では規制できず、大きな社会問題となってくるだろう。そ... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| この研究では、人々の利用する情報メディアに目を向け、プロ野球という議題に関しての調査を行い、少数派意見所持者が多数派意見所持者よりもインターネットによる情報収集を行っているという仮説を提唱し、プロ野球ファンにおいてこの仮説に適合性する緩やかな傾... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| マスメディアの受け手が犯人視報道によって事実誤認を引き起こすかについて研究した。この研究は基本的に主にジャーナリズム研究、さらにマスコミ効果研究の分野に渡っている。 事件名と容疑者名で報道した場合において、どのような事実誤認に差があるかについて... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| 現在、多くのホームページが作成されている。作成方法がマニュアル化され、容易なものになっているが、「色」に関する基準が曖昧である。人が「色」から受けるイメージは非常に強い。「色」ひとつで人の心をとらえることもできるし、その逆もありうる。よりよいホー... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| 近年、環境問題に対する関心が大きくなっている。平成13年度には家電リサイクル法など新しい政策が発表されている。 市民の生活は快適性と利便性を求めた結果、大量生産-大量消費を前提とした生産システムが構築された。商店やデパートに行けば商品はたくさん... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| 近年、世間に不景気風が吹いている中、少なからず打撃は受けたものの、そんな不景気風などものともしないような勢いで注目を浴びているのがフランチャイズチェーンである。このようなことから、なぜこの不況の中、注目を集め成長しているのかということに疑問を持... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| 不特定多数が参加する電子掲示板上では、もし、なりすましや改竄が行われるうと、その電子掲示板上の情報に対する信頼性が失われてしまう。 なりすましとは他人の名前で無責任な発言を電子掲示板上に載せる事である。改竄は当然ながら不正な情報に変更してしまう... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| たばこ消費量の変動においてマス・コミ情報量が影響を与えるかという問いについて、新聞記事をマス・コミ情報量と定義して分析をおこなった。たばこについてマイナスイメージを与える情報を数種のマイナスイメージ記事に分類、たばこについてプラスイメージを与え... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| 現在、自治体は本格的に競争の時代を迎えている。自己変革し自己責任の強い自治体に変わることが求められている。それは、中央や外部からの影響による外来型スタイルからの施策展開ではなく、自治体内部からの住民・納税者・ユーザーを起点とした内発型スタイルか... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| 抄録 現在消費者優位の時代ではいかにしてお客が満足してくれるような商品・サービスを企業が提供するかが生き残りのカギとなり、さらにそのお客を顧客に発展させることが重要となってくる。 消費者のニーズを知る手段としてアンケートが考えられる。さらにこのアン... | |||
| 2002年 | |||
 | |||
| 私達の暮らしは大量生産と大量消費という構図のもとに成り立っている。国民が、大量に生産された物を、過剰消費する事によって経済が活発になっているのである。しかし、このような悪循環の大量生産・消費が続けられると、廃棄物量が増大し、地球環境に多大な負荷... | |||
| 2002年 | |||