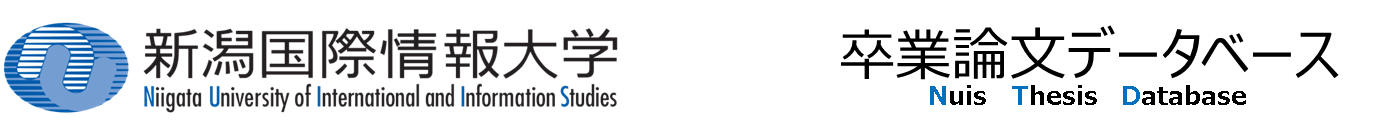抄 録 検 索
[全8100件] : 現在のページ「362」 ---7221個目から7240個目のデータを表示---
 | 1945年に終了した第二次世界大戦は、世界中を巻き込んだ戦争であった。この戦争によって物質的な損害と人道に反した被害がもたらされた。これらは、戦争が終了し、世界秩序を再構築する上での新しい問題となった。この中で、人道に反した被害の問題として最も大... | 2000年 | |
 | 1982年に、日本は、アジアをはじめとする国々から歴史教科書の日本の加害の歴史事実を記述していないとして非難された。それから、日本の歴史教科書は歴史事実を記述するようになってきたが、1999年の朝日新聞社と東亜日報社の日韓合同世論調査では、歴史... | 2000年 | |
 | 私たちは生活の中で言葉を用いて生活をする。そして、その言葉を何気なく使いこなしている。人間が用いている言葉にはどんな役割があり、また私たちにどんな影響を与えているのだろうか。私たちは、人間同士でコミュニケーションを行う。お互いの考えや気持ちを伝え... | 2000年 | |
 | 98年9月、ドイツで連邦議会(下院)総選挙が行われた。結果、コール率いる当時与党のCDU・CSUがシュレーダー率いるSPD に敗れ、ゲアハルト・シュレーダーが新首相に選ばれた。シュレーダーはブレア流の「第3の道」を意識した政治家で、本来左派のSPD内では異色な存在... | 2000年 | |
 | 現在では、結婚式場がたくさんあるにもかかわらず、晩婚化や非婚時代といったことにより婚姻率は下がりつづけ、ブライダル業界に危機感が生じているといった状況があるようだ。昔から繰り返し行われている「結婚」。けれど、そこにはいろいろな歴史があり、また人... | 2000年 | |
 | 現在、本書の内容を紹介した『福祉』という問題は、今日ますます大きくなっている。本章に書いてあることがすでに実行されていたりしている部分があるかも知れない。確定拠出型年金―日本版401k―の2000年導入、それに対する税制優遇措置などその良い例であ... | 2000年 | |
 | 99年1月1日、EU加盟国中11カ国によって欧州単一通貨ユーロは導入された。これは「世紀のイヴェント」と呼ばれるほど注目された。なぜなら、これまで幾度か行われてきた通貨同盟とはまったく異なる性質をしているからである。ユーロは、今までEUが進めてきた経済統... | 2000年 | |
 | 大学の4年間で、私は授業を通して2、3の異文化と様々な思想に触れることが出来た。私の大学ではいわゆる「環日本海」の国々、つまりロシア、中国、朝鮮の文化とアメリカの文化を勉強出来る。私は主に中国とアメリカの文化についての講義を受講した。それに付随し... | 2000年 | |
 | 私が金融ビッグバンをテーマに選んだ理由は、就職活動を通じて不景気を肌で感じたことが大きな理由である。今年は就職の雇用情勢が悪く、新入社員を採用する企業も例年よりも少なく、また各企業もリストラを進めていて景気の上昇する気配が感じられなかった。なぜ今... | 2000年 | |
 | 「生涯学習」ということばは、すでに社会に浸透しており、これからは生涯学習の時代になるといわれている。人々が学習を通じて自己の能力と可能性を最大限に伸ばし、それぞれに自己実現をはかっていく社会を、生涯学習社会とよぶことができるが、これを実現してい... | 2000年 | |
 | 私は女性の社会進出を卒業研究に取り上げた。数十年前までは、女性は結婚したら仕事を辞め専業主婦になる傾向があった。しかし最近では結婚しても仕事を続ける女性や結婚より仕事を優先し結婚を遅らせる女性も増えた。女性のこのような動きと並んで、今日日本は高齢... | 2000年 | |
 | 私がフォルクスワーゲン車に興味を持ち始めたのは、今から18年前ころである。叔父が黄色のゴルフ・に乗っていて、よくドライブに連れて行ってもらった。当時の私の目には、ゴルフという車は他の車とさほど変わらないものとして写っていた。しかし、私が小学校2年生... | 2000年 | |
 | 現在の世界人口は52億人となっているが、その22%は中国の総人口に達する。中国は地球上かつてない人口超大国となっている。中国では人口が多いということで、食糧不足、出稼ぎ労働者問題、失業問題、社会、文化、モラルの危機的状態の発生などの問題が起こっている... | 2000年 | |
 | 中国で指折りの思想家と言われた朱子の思想である朱子学が高麗末の朝鮮に伝来して以来、その概念である理と気という二物をめぐって主理派と主気派の二つの学派が互いにしのぎをけずっていた。主理派の代表的人物は李滉であり、主気派の代表的人物は徐敬徳である。そ... | 2000年 | |
 | まず、私が卒業論文の題材に、封神演義を選ぶ事になった理由をかきたいとおもいます。私は、大学1、2、3、年と中国語をりっ修し、中国語はもちろんですが、中国の文化も少し学びました。中国の文化をまなんでいるうちに、中国の書物に興味をもつようになりました。... | 2000年 | |
 | 1986年4月26日、ウクライナ(当時はソ連)のチェルノブイリ原発で起こったかつてない大事故について取り上げた。当時、ゴルバチョフ書記長の情報公開の拡大などを唱えた就任演説によって、西側諸国の報道陣の間でこの事故に対するソ連の対応は注目を集めた。し... | 2000年 | |
 | 1991年のソ連邦崩壊にともなって、これまでソ連邦を構成していた共和国間で独立国家共同体(CIS)が創設された。各CIS諸国が望んでいることは、旧ソ連時代の枠組みではなく、独立した国家間関係を強化することであった。しかし、政治的・経済的基盤を持た... | 2000年 | |
 | 自由とファッションにおける心理的なメディアとなるものを主題とする。普遍的で無意識的な自由への多義的な渇望は、社会過程の産物であり、それゆえ人間の性格のなかに働いている無意識的な力の働きとそれが外界に依存しているということ。社会的拘束からの自由は... | 2000年 | |
 | 喜び、怒り、哀しみ、楽しみ。私達の人生は多様な感情とともにある。様々な感性の人間が出会い、交わり、別れをとおして多様な人生を生き、愛し合い、慈しみ合い、時には、憎しみや葛藤を経験する。その中で人生というドラマ、日々の生活が展開されている。 感性... | 2000年 | |
 | なんのひねりもないタイトル通り、私が大学3年後期にあたる98年の秋から99年の冬にかけて中国、北京の「北京語言文化大学」に留学したときのことを書いた。現地での体験をまとめて記録したというより、自分が感じたことや思ったことをどこまで文章に落とせるも... | 2000年 |